親が亡くなり、悲しみに暮れる暇もなく訪れた実家。そこは、思い出の詰まった「実家」ではなく、まさかのゴミ屋敷になっていました。
戸惑いとショック、そして怒りや後悔——今回は、遺品整理を通じて直面した「親の家がゴミ屋敷だった」という現実について、私の体験を交えてお話しします。
入った瞬間、鼻を突く臭いと足の踏み場のない室内
久しぶりに足を踏み入れた実家。玄関を開けた瞬間、カビ臭い空気とともに、視界いっぱいに広がる「ゴミの山」。
雑誌や新聞、レジ袋に詰まった謎の生活ゴミ、使わなくなった家電……。足の踏み場もなく、床は見えず、部屋の中はまるで迷路のようでした。
父は数年前に他界し、母は一人暮らしを続けていました。数ヶ月前に入院し、そのまま帰らぬ人となったのですが、まさか、こんな状態で暮らしていたなんて——。
「もったいない」が積もってゴミになる
なぜ、こんなことになったのか?母は昔から物を大切にする人で、「まだ使える」「誰かにあげるかも」「いつか必要になるかも」が口癖でした。
最初は整理整頓ができていたはず。でも高齢になるにつれて、片付ける体力も判断力も落ちていったのでしょう。気づけば、自分では片付けられない状態に。
そして誰にも相談できないまま、ゴミがゴミを呼ぶ「ゴミ屋敷」と化してしまったのです。
遺品整理どころじゃない、「片付け」からのスタート
一般的な遺品整理は、ある程度片付いた家から始まります。でも、ゴミ屋敷化した家では、まず「清掃」と「ゴミの仕分け」からスタート。
生ゴミや腐った食品、害虫が湧いたキッチン、足の踏み場のない部屋、埃まみれの布団……。
遺品に触れる前に、まずは防護マスクと手袋を着けての掃除です。プロの遺品整理業者に相談したところ、「これは通常の整理ではなく、ゴミ屋敷対応の作業ですね」と言われました。
費用も跳ね上がります。通常の1Kの遺品整理が5〜8万円ほどだとしても、ゴミ屋敷となればその倍以上、10〜30万円かかることも珍しくありません。
精神的なダメージも大きい
家の中を片付けていく中で、確かに思い出の品は出てきました。写真、手紙、家族旅行のお土産——懐かしさに涙がこぼれる瞬間もありました。
でも、正直なところ、それ以上に「なんでこんなことになるまで放っておいたんだろう」「気づいてあげられなかった自分が情けない」といった後悔や自己嫌悪の感情の方が強かったです。
怒りも湧いてきました。「せめてちゃんと片付けておいてほしかった」と。でも、同時に「一人で頑張っていたんだな」と思うと、胸が苦しくなります。
片付け終わったあとに見えてきたもの
数週間かけて、ようやくゴミをすべて処分し、最低限の整理が終わったとき、部屋には静けさが戻りました。
そしてその静けさが、亡き母の孤独を物語っているように思えて、心が締め付けられました。
私たち子どもが忙しさを理由に実家を訪れる機会が減り、何気ない「どう? 元気にしてる?」の一言すら足りなかったのかもしれない。
ゴミ屋敷にならないために、今からできること
今回の経験から、痛感したことがあります。それは、「親の家を気にかけること」は、思いやりのひとつだということです。
- 定期的に実家に顔を出す
- 物の持ちすぎをやんわり注意する
- 一緒に片付けを手伝う
- 生前整理を提案する
年老いた親の「片付けられない」は、意外と早く始まっているかもしれません。手遅れになる前に、できることはたくさんあります。
まとめ
遺品整理というだけでも大変なのに、それが「ゴミ屋敷」だった場合、肉体的にも精神的にも想像以上の負担がかかります。
今回の体験は、親の死という悲しみのなかに、私にたくさんの“気づき”を残してくれました。
もし今、少しでも「うちの親、大丈夫かな?」と心に引っかかるものがあるなら、ぜひ一度、実家を訪れてみてください。
その一歩が、将来の大きな後悔を防ぐかもしれません。

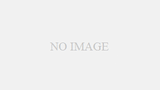
コメント