1. はじめに
食生活の健康を考える上で「塩分摂取量」は重要なポイントです。特に高血圧や生活習慣病の予防には、日頃から塩分を意識することが不可欠です。しかし、「どの食品にどれくらいの塩分が含まれているのか?」を正確に把握するのは意外と難しいものです。
そこで、本記事では 「食品の塩分表示の正しい見方」 をわかりやすく解説し、健康的な食生活のための実践的な知識をお届けします。
2. 塩分表示とは?
食品には 「ナトリウム(mg)」 や 「食塩相当量(g)」 などの塩分に関する情報が記載されています。これらの表示を正しく理解することで、無意識のうちに塩分を摂りすぎるリスクを防ぐことができます。
2.1 ナトリウムと食塩相当量の違い
食品の栄養成分表示には 「ナトリウム」 と 「食塩相当量」 の2つの表記が使われることがあります。
| 表記 | 意味 | 計算式 |
|---|---|---|
| ナトリウム(mg) | 塩分の主成分であるナトリウムの量 | 食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54 ÷1000 |
| 食塩相当量(g) | ナトリウムが食塩に換算された量 | そのまま塩分量として考えられる |
例えば、食品の成分表示に ナトリウム1000mg と書かれていた場合、それを食塩相当量に換算すると 1g × 2.54 = 2.54g の塩分を摂取することになります。
最近では、消費者が分かりやすいように 「食塩相当量(g)」 で表記されることが増えていますが、ナトリウム(mg)表記のみの場合は計算が必要 です。
3. 日本人の1日の適正な塩分摂取量
厚生労働省の 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」 によると、成人の1日の塩分摂取目標は以下の通りです。
- 成人男性:7.5g未満
- 成人女性:6.5g未満
- 高血圧の人:6g未満が推奨
しかし、実際の日本人の 平均塩分摂取量は約10g と、目標よりも高い傾向があります。多くの人が減塩を意識する必要があると言えるでしょう。
4. 食品ごとの塩分量の目安
食品ごとにどの程度の塩分が含まれているのかを知っておくと、日常生活の中で塩分をコントロールしやすくなります。
4.1 高塩分の食品(摂取に注意)
| 食品 | 食塩相当量(g) |
|---|---|
| しょうゆ(大さじ1) | 約2.6g |
| 味噌(大さじ1) | 約2.2g |
| インスタントラーメン(1袋) | 約5.5g |
| 梅干し(1個) | 約2g |
| 漬物(たくあん3切れ) | 約1.5g |
| コンビニおにぎり(1個) | 約1.2g |
4.2 塩分控えめの食品(おすすめ)
| 食品 | 食塩相当量(g) |
|---|---|
| 白米(1杯) | 0g |
| 無塩ナッツ(20g) | 0g |
| 野菜(100g) | 0〜0.1g |
| ヨーグルト(100g) | 0.1g |
| ささみ(100g) | 0.1g |
特に 加工食品や外食 は塩分が多く含まれていることが多いので、成分表示を確認しながら選ぶことが大切です。
5. 塩分表示を活用した減塩のコツ
5.1 ナトリウム(mg)表示の場合は換算する
前述の計算式を使って、ナトリウム量を食塩相当量に換算しましょう。例えば、ナトリウム500mgなら、食塩相当量は 1.27g(500×2.54÷1000) です。
5.2 1食あたりの塩分を意識する
1日7g以下の塩分摂取を目標にすると、1食あたり 2〜2.5g に抑えるのが理想です。食品の塩分表示を見ながら、1食の合計が適切な範囲に収まるように調整しましょう。
5.3 「減塩」表示の商品を活用する
最近では、「減塩しょうゆ」「減塩味噌」「減塩梅干し」など、通常よりも塩分をカットした食品が多く販売されています。これらを上手に活用することで、無理なく塩分を減らせます。
5.4 外食時は「スープを飲み干さない」
ラーメンや味噌汁のスープには大量の塩分が含まれています。例えば、ラーメンのスープを全て飲むと 約4g以上の塩分 を摂取することになります。減塩を意識するなら、スープは半分以上残すのが理想です。
6. まとめ
食品の塩分表示を正しく理解することは、健康的な食生活の第一歩です。「ナトリウム」と「食塩相当量」の違いを知り、日々の食事でどれくらいの塩分を摂取しているのかを意識することが大切です。
この記事のポイントまとめ
✅ ナトリウム(mg)表記は食塩相当量(g)に換算してチェック
✅ 1日の塩分摂取量の目安(7.5g未満)を意識する
✅ 高塩分の食品は控えめに、減塩食品を活用する
✅ 外食や加工食品の塩分に注意し、スープは残す
毎日の食生活で少しずつ塩分を減らし、健康的な食習慣を身につけましょう!

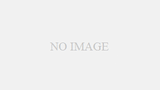
コメント